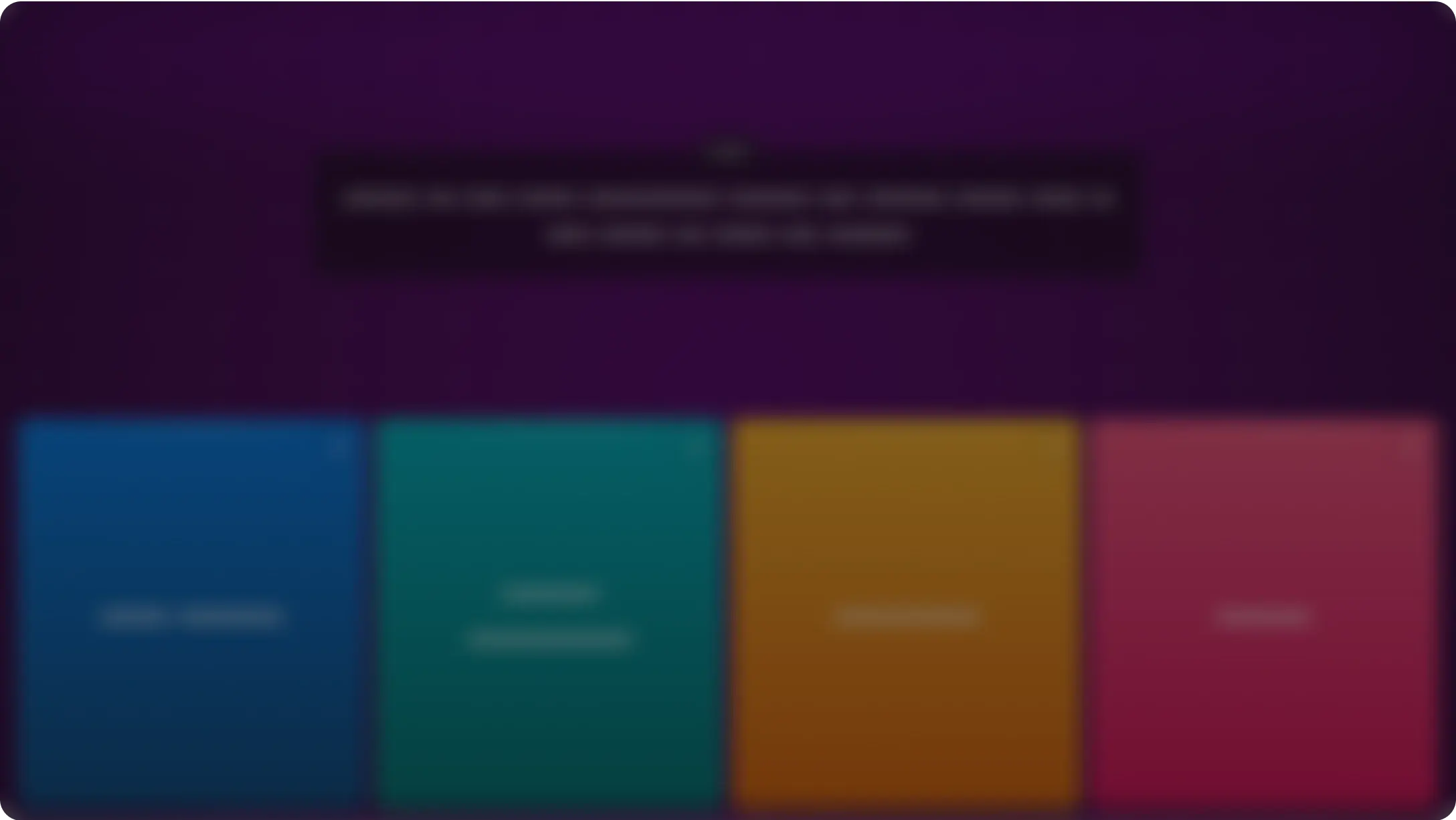ITパスポート試験 テクノロジ系2
Quiz
•
Computers
•
10th Grade
•
Practice Problem
•
Hard
T Shibasaki
Used 4+ times
FREE Resource
Enhance your content in a minute
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 2 pts
ワイルドカードに関する次の記述中のa,bに入れる字句の適切な組合せはどれか。
任意の1文字を表す"?"と,長さゼロ以上の任意の文字列を表す"*"を使った文字列の検索について考える。( a )では,"データ"を含む全ての文字列が該当する。また,( b )では,"データ"で終わる全ての文字列が該当する。
令和元年秋期 問99出題
a.?データ*
b.*データ
a.?データ*
b.?データ
a.*データ*
b.*データ
a.*データ*
b.?データ
Answer explanation
〔( a )について〕
"データ"を含む全ての文字列にマッチさせるには、"データ"の前後に長さゼロ以上の任意の文字列を表す"*"を付けます。こうすれば前後にどのような文字列が付いていても、全く付いていなくても"データ"さえ入っていれば該当します。「*データ*」は、単なる"データ"、"データベース"、"電子データ"、"旧データファイル"などの"データ"を含む文字列全てにマッチします。なお、「?データ*」は任意の1文字から始まり、2~4文字目がデータとなる文字列を表すので、"旧データファイル"にはマッチしますが、"データ"、"データベース"、"電子データ"にはマッチしません。
〔( b )について〕
"データ"で終わる文字列にマッチさせるには、"データ"の前に"*"を付けます。「*データ」は、"データ"、"電子データ"、"新データ"などの末尾が"データ"である文字列にマッチします。なお、「?データ」は任意の1文字+データとなっている文字列を表すので、"新データ"にはマッチしますが、"データ"、"電子データ"にはマッチしません。
したがって、a=*データ*、b=*データ となる。
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 2 pts
3人の候補者の中から兼任も許す方法で委員長と書記を1名ずつ選ぶ場合,3人の中から委員長1名の選び方が3通りで,3人の中から書記1名の選び方が3通りであるので,委員長と書記の選び方は全部で9通りある。5人の候補者の中から兼任も許す方法で委員長と書記を1名ずつ選ぶ場合,選び方は何通りあるか。
令和元年秋期 問72出題
5
10
20
25
Answer explanation
5人の中から委員長1名を選ぶ方法は5通り、5人の中から書記1名は5通りです。委員長と書記の兼任が許されているので、委員長の選び方のそれぞれについて書記の選び方が5通りあることになります。したがって選び方は「5通り×5通り=25通り」です。
ちなみに、兼任を許さない場合は5人から1名委員長を選び、残った4人から書記1名を選ぶことになるので「5通り×4通り=20通り」の選び方があります。5人の中から委員長1名を選ぶ方法は5通り、5人の中から書記1名は5通りです。
委員長と書記の兼任が許されているので、委員長の選び方のそれぞれについて書記の選び方が5通りあることになります。
ちなみに、兼任を許さない場合は5人から1名委員長を選び、残った4人から書記1名を選ぶことになるので「5通り×4通り=20通り」の選び方があります。
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 2 pts
推論に関する次の記述中のa,bに入れる字句の適切な組合せはどれか。
( a )は,個々の事例を基にして,事例に共通する規則を得る方法であり,得られた規則は( b )。
令和4年春期 問57出題
a.帰納推論
b.成立しないことがある
a.帰納推論
b.常に成立する
a.演繹(えんえき)推論
b.成立しないことがある
a.演繹(えんえき)推論
b.常に成立する
Answer explanation
推論とは、既に知っている事実をもとにして未知の事実を予想する方法です。演繹推論、帰納推論は次のような推論の方法です。
演繹推論(えんえきすいろん)
普遍的な事実を"大前提"、個別の事実を"小前提"とし、これらを踏まえて理論的に結論を導く方法
例)人間は必ず死ぬ(大前提) → ソクラテスは人間である(小前提) → ソクラテスは死ぬだろう(結論)
帰納推論(きのうすいろん)
複数の既成事実から共通規則や類似点を見つけ、結論を導く方法
例)ヤギはメーと鳴く(事例)、牛はモーと鳴く(事例)、カラスはカーと鳴く(事例) → 動物はそれぞれ異なる声で鳴く(結論)
設問の記述では、個々の事例から共通する規則を導いているので帰納推論になります。
帰納推論の結果はその事例内で認められる結果であり、全体を代表しているとは限りません。反証が見つかるなどして成立しないこともあります。
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 2 pts
情報の表現方法に関する次の記述中のa~cに入れる字句の組合せはどれか。
情報を,連続する可変な物理量(長さ,角度,電圧など)で表したものを( a )データといい,離散的な数値で表したものを( b )データという。音楽や楽曲などの配布に利用されるCDは,情報を( c )データとして格納する光ディスク媒体の一つである。
令和3年春期 問89出題
a.アナログ
b.ディジタル
c.ディジタル
a.アナログ
b.ディジタル
c.アナログ
a.ディジタル
b.アナログ
c.アナログ
a.ディジタル
b.アナログ
c.ディジタル
Answer explanation
アナログは連続的に変化する物理量を表す言葉、ディジタルは連続していない(離散的な)量を表す言葉です。時計を例にすると、アナログ時計は秒針が連続的に滑らかに動いていて秒と秒の間の値が存在しますが、ディジタル時計は1、2、…というように秒の間の値がないというイメージです。音楽や楽曲などの配布に利用される媒体のうち、レコードやカセットテープはアナログデータ、CDやMP3はディジタルデータです。
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 2 pts
A3判の紙の長辺を半分に折ると,A4判の大きさになり,短辺:長辺の比率は変わらない。A3判の長辺はA4判の長辺のおよそ何倍か。
令和4年春期 問93出題
1.41
1.5
1.73
2
Answer explanation
A3判の長辺はA5判の長辺の2倍の長さになっています。
A5→A4、A4→A3で長辺の倍率は同じはずなので、用紙サイズが1つ大きくなるときの長辺の倍率を"n"とすると、A4判の長辺はA5判の長辺のn倍、A3判の長辺はA5判の長辺のn2倍になります。
この関係を式に表すと、1×n×n=2 n2=2 n=√2≒1.41
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 2 pts
ディープラーニングに関する記述として,最も適切なものはどれか。
令和4年春期 問67出題
インターネット上に提示された教材を使って,距離や時間の制約を受けることなく,習熟度に応じて学習をする方法である。
コンピュータが大量のデータを分析し,ニューラルネットワークを用いて自ら規則性を見つけ出し,推論や判断を行う。
体系的に分類された特定分野の専門的な知識から,適切な回答を提供する。
一人一人の習熟度,理解に応じて,問題の難易度や必要とする知識,スキルを推定する。
Answer explanation
ディープラーニング(深層学習)は、コンピュータに自ら学習する能力を与える機械学習の一つで、人間や動物の脳神経をモデル化したアルゴリズム(ニューラルネットワーク)を多層化したものを用意し、それに十分な量のデータを与えることで、コンピュータが人間の力なしに自律的に特徴点やパターンを学習することをいいます。人工知能分野における要素技術の1つであり、これまでの機械学習よりも精度が優れていることから、近年におけるAIの急激な発展と普及の根幹を支える技術となっています。「ニューラルネットワーク」というキーワードから、これがディープラーニングに関する記述であることがわかります。
インターネット上に提示された教材を使って,距離や時間の制約を受けることなく,習熟度に応じて学習をする方法である。=eラーニングの説明です。
コンピュータが大量のデータを分析し,ニューラルネットワークを用いて自ら規則性を見つけ出し,推論や判断を行う。=ディープラーニングの説明です。
体系的に分類された特定分野の専門的な知識から,適切な回答を提供する。=エキスパートシステムの説明です。
一人一人の習熟度,理解に応じて,問題の難易度や必要とする知識,スキルを推定する。=アダプティブラーニングの説明です。
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 2 pts
次のデータの平均値と中央値の組合せはどれか。
〔データ〕10,20,20,20,40,50,100,440,2000
令和4年春期 問59出題
平均値:20
中央値:40
平均値:40
中央値:20
平均値:300
中央値:20
平均値:300
中央値:40
Answer explanation
データ全体を代表する値として、平均値、中央値、最頻値があります。
平均値
データの値を合計して、その合計値をデータの個数で割った値 中央値 データを値の大小で並べたときに中央に位置する値※データの個数が偶数のときは中央の値が2つになるので、その2つの平均値
最頻値
データの中で最も多く出現する値
【平均値】10+20+20+20+40+50+100+440+2000=2700 2700÷9=300
【中央値】設問のデータは既に小さい順に並んでいるので、その中央(9個中5番目)に位置する40
Create a free account and access millions of resources
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google
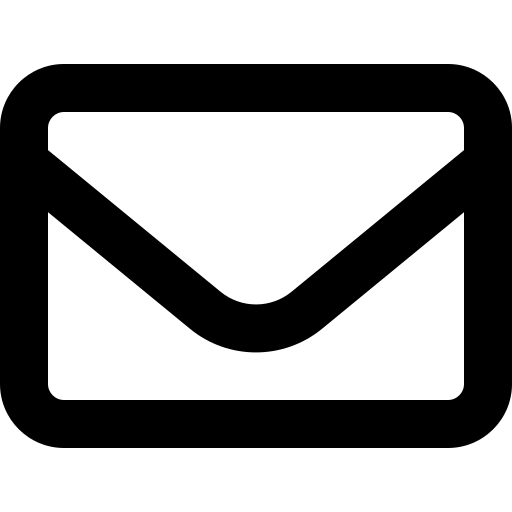
Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?
Similar Resources on Wayground

5 questions
第2回
Quiz
•
KG - Professional Dev...

12 questions
10_03 ITサービスマネジメント
Quiz
•
1st - 12th Grade

13 questions
情報に関する法規や制度
Quiz
•
10th Grade

15 questions
情報1学期末小テスト
Quiz
•
9th - 12th Grade

10 questions
ストラテジまとめ⑤
Quiz
•
9th - 12th Grade

8 questions
11_オブジェクト指向・プログラムの性質
Quiz
•
9th - 12th Grade

7 questions
1範囲 情報の科学⑥
Quiz
•
10th Grade
Popular Resources on Wayground

5 questions
This is not a...winter edition (Drawing game)
Quiz
•
1st - 5th Grade

15 questions
4:3 Model Multiplication of Decimals by Whole Numbers
Quiz
•
5th Grade

25 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
5th Grade

10 questions
The Best Christmas Pageant Ever Chapters 1 & 2
Quiz
•
4th Grade

12 questions
Unit 4 Review Day
Quiz
•
3rd Grade

10 questions
Identify Iconic Christmas Movie Scenes
Interactive video
•
6th - 10th Grade

20 questions
Christmas Trivia
Quiz
•
6th - 8th Grade

18 questions
Kids Christmas Trivia
Quiz
•
KG - 5th Grade