
化学 小学校単元
Authored by Sayaka Komatsuda
Chemistry
6th - 8th Grade
106 Questions
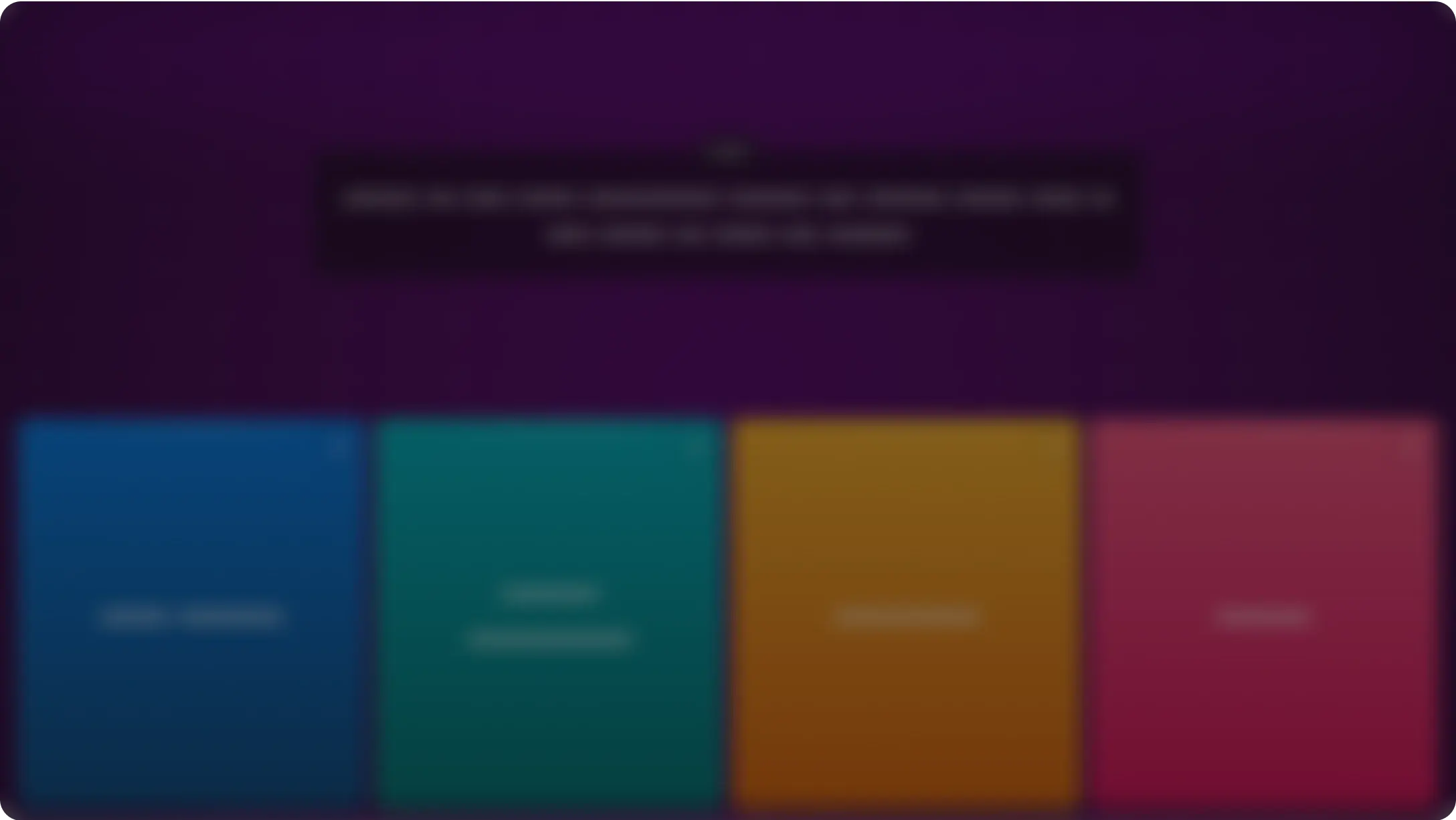
AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
1.
MULTIPLE SELECT QUESTION
1 min • 1 pt
ガスバーナーの使い方で気を付けることを次のうちからすべて選びなさい
Answer explanation
火を消した後はガスバーナーの上部がかなり熱くなっているので、火を消した後はガスバーナーが冷めるまで待ってから片づけることが正解である。よって選択肢の3は火を消してから時間をおいていないので間違っている。
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
二酸化炭素を通すと白く濁る水溶液はどれか
Answer explanation
石灰水に二酸化炭素を吹き込むと炭酸カルシウムが生成し、白く濁る。さらに多量の二酸化炭素を吹き込むと透明になる。 化学式:Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O さらに多量の二酸化炭素を吹き込むと 化学式:CaCO3+CO2 +H2O→Ca(HCO3)2
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
ガスバーナーの使い方について正しいものを選べ。 1,コックを開ける 2,ガスの元栓を開ける 3,ガス調節ねじを開ける 4,空気調節ねじを開ける 5,火をつける
Answer explanation
ガスバーナーに火をつける際は 1,コックとガスの音栓が閉まっていることを確認する。 2,調節ねじが軽く締まっていることを確認する 3,ガスの元栓を開く 4,コックを開ける 5,マッチに火をつける 6,ガス調節ねじを開けて火を近づける 7,ガス調節ねじを開けたり閉めたりして火の大きさを調節する 8,空気調節ねじを調節して、火が青い炎になるようにする 赤い炎であると、不完全燃焼を起こし一酸化炭素が発生してしまうため、アオイホノオにして完全燃焼が起きるようにする。
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
上皿てんびんの正しい片付け方はどれ?
Answer explanation
片付ける時は上皿てんびんを長持ちさせるために片側に2枚重ねておく。両側に同じ枚数ずつ置いたり両方の皿を取ったりしてしまうと両側が同じ重さになってしまい、天秤が揺れ、摩耗して壊れやすくなってしまう。
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
理科室の使い方に関して、誤っているものを次のうちから1つ選びましょう。
Answer explanation
1…単独実験は極めて危険である。万が一のとき、助けてくれる人がいなかったために死亡するというケースが十分考えられるため正しい。 2...実験中はその実験に集中する。実験中は常に自分の周りに注意を払い、怪我などの危険を事前に回避できるよう、心がける。よって正しい。 3...使用した薬品は有害なものや環境を汚染するものがあるので、不用意に流しに捨てず、指定した場所に回収する。 4...火が出た、液がはねて付いた、ガラス器具を割った、気体を吸って気分が悪くなった等、細かいことでもすぐに担任の先生に報告する。
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
太陽が地球の地表を熱するのは、なんという熱の伝わり方によるか。
Answer explanation
選択肢1の対流とは、空気や液体が温度差により流動することで、熱が伝わることである。例:鍋でお湯を沸かす時には、鍋に接している部分から熱くなるため対流が起き、それによって熱が均一になる。 選択肢2の熱伝導とは、隣接する分子の動きが伝わることで熱くなることである。 例:フライパンで炒め物をするときに、野菜はフライパンに接しているため直接熱が伝わる。 選択肢3の放射とは、粒子線や電磁波によって分子が動くことで熱が生み出され、物質の移動を伴わないことである。ここでは、太陽からの電磁波(特に可視光線)により地表の分子が動くことで地表が熱くなる。 選択肢4の潜熱とは、水の状態変化に伴って出入りする熱のことである。 例:打ち水をすると温度が下がるが、これは水が蒸発して水蒸気に変化する際に熱が吸収されるからである。この熱は、水蒸気が水滴になって雲になるときなどに放出される。これが潜熱と呼ばれる。 よって、正解は選択肢3の放射となる。
7.
MULTIPLE SELECT QUESTION
1 min • 1 pt
薄い塩酸と反応する物質を全て答えよ
Answer explanation
これは物質のイオン化傾向から説明できる。実は1から4の順にイオン化傾向が小さくなっておりイオン化傾向が大きいほど反応性が高い。鉛までが希塩酸などの薄い酸と反応してH2を発生する。よって鉛よりイオン化傾向が大きいマグネシウムとアルミニウムが塩酸と反応し答えは1,2となる。また、イオン化傾向からは空気中での反応性や水との反応性も読み取ることができる。銅は酸化力の強い酸と反応し、常温では徐々に酸化され表面に酸化皮膜ができる。水とは反応しない。金は基本的に反応しにくく、空気中、水とは反応しない。酸は王水と反応する。 以下は反応式である。 Mg+2HCL→MgCL2+H2 2AL+6HCL→2ALCL3+3H2
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google
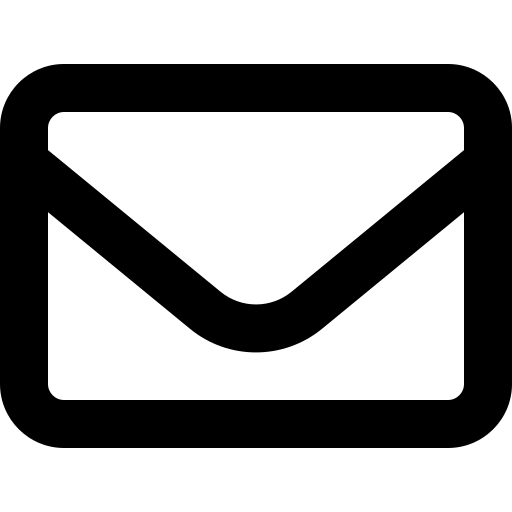
Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?
Popular Resources on Wayground

5 questions
This is not a...winter edition (Drawing game)
Quiz
•
1st - 5th Grade

25 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
5th Grade

10 questions
Identify Iconic Christmas Movie Scenes
Interactive video
•
6th - 10th Grade

20 questions
Christmas Trivia
Quiz
•
6th - 8th Grade

18 questions
Kids Christmas Trivia
Quiz
•
KG - 5th Grade

11 questions
How well do you know your Christmas Characters?
Lesson
•
3rd Grade

14 questions
Christmas Trivia
Quiz
•
5th Grade

20 questions
How the Grinch Stole Christmas
Quiz
•
5th Grade